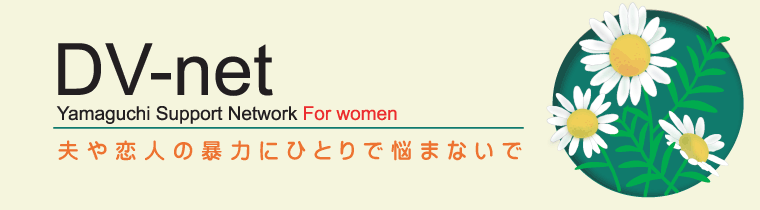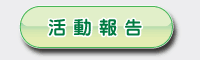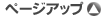ニュースレター18号
2011/01/06
 |
| ニュースレター |
サバイバーへの支援
師走の忙しい季節となりました。いかがお過ごしでしょうか。
4月からたくさんの事業が始まり、年度当初の4月には考えられなかったほどの事業をやっています。これからの事業としては、山口県との協働事業として、1月23日(日曜日)「愛情という名の支配」について信田さよ子氏の講演会を予定しています。また平成23年3月31日までの事業として、独立行政法人福祉医療機構の助成による「DV被害母子のヒーリングケア」、山口県「配偶者からの暴力被害者のための自助グループ委託事業」、宇部市「配偶者等暴力相談一部委託事業」、内閣府モデル事業「定着促進のためのプログラム」として「仲間との出会いの場プログラム(居場所づくり)」などの事業を実施しています。
これまでも、DV被害者が自宅でシェルターを出た後のケアとしての自立支援について、どうすれば元に戻らずに安全に安心して暮らせるかを何年も模索してきました。今年度は山口県からも認められ自助グループに委託事業を受けることができました。また、内閣府のモデル事業としても取り組むことができるようになりました。少しずつこれまでの事業の取組が実を結びつつあるようです。まだまだ試行錯誤は続きますが、予算化されて取り組むことができたことは大きな成果といえるでしょう。特に昨年好評だった「お正月会」ですが、今年は予算が取れたので、温泉つきのお料理を楽しむことができそうです。お正月は一人で過ごさねばならない人たちにとって、家族の賑わいがない、孤独でとても辛いものです。すこしでもそれを緩和できればと思って企画しています。
相談事業ですが、宇部市の「配偶者等からの暴力相談一部委託事業」を受けて7月から来年3月31日まで行います。平日9時~16時までの相談でかなりハードです。たくさんのケースが次々に起き、その対応に振り回されています。一人ひとりの持っておられる課題は違いますので、市が持っている支援にどこまでつなぐことができ、安心して暮らすことができるように本人とも相談しながら進めているところです。7月以降に関わった部署は、警察署、県男女共同参画相談センター、公共職業安定所、社会福祉協議会、男女共同参画課、市民課、社会福祉課、高齢福祉課、保険年金課、こども福祉課、保健推進課、学校教育課、住宅課、山口女性サポートネットワークなど多岐にわたっています。これらは、ちょうど宇部市DV防止支援ネットワークの属している関係部署や団体です。これまでの相談経験と自立支援の経験を生かして、宇部市の相談業務でも最大限の支援をしているところです。この相談事業は3月で終わりますが、この経験を市にも私にも財産として残せるよう努力していくつもりです。
今年度は、念願のステップハウスが2室できました。ステップハウスというのは、シェルターほどの厳しい管理はなく、通学や仕事にも通える施設です。2人の提供者によって可能となりました。今、2人の被害者が入所されています。このようなことも可能になっていくことを実感している今日この頃です。
『DV・虐待加害者の実態を知る』
ランディ・バンクロフト Lundy Bancroft【著】
高橋 睦子 中島 幸子 山口 のり子監訳 明石書店 2008
ランディ・バンクロフトさんはアメリカでDV加害者カウンセラーとして1000人を超える加害者に接してきた人です。N・Mさんにこの本の概要をまとめてもらいました。概 要
この本が一貫して主張していることは
「DVによる虐待は被害者である彼女や子供には何の原因もなく、全ては加害者の価値観や考え方によって引き起こされる」ということであります。
その考え方とは以下の様なものであり、この考え方は文化・宗教・法制度により培われてきた一面があるため、加害者への擁護者や被害者への批判者がなくならない現状があります。
・彼は所有意識を持っている。・・・考え方の核心
・彼は彼女や子供をコントロールしようとする。
・彼は特権意識を持っている。
・彼女を軽んじて、自分の方が優れていると考えている。
・彼は虐待を愛だと考えている。
・彼は自分が正しいと思い込んでいる。
そして、彼は“物事を正反対に捻じ曲げてしまう”・“パートナーを操る”・“外面が良い”というような手口を使って周囲を味方につけ、彼女や子供の心を不安定な状態にしておき、所有意識・特権意識の満足を図っているのです。
「虐待はお互いの関わり合いに問題があって起きるものではありません」。したがって、彼女の自省や忍耐・懇願は彼を増長させるだけで、虐待がひどくなる事があっても終わることはありません。
“DV被害者には、加害者を変えることも変わるのを助けることもできません。できることは、彼に自分は変わらなければならないと感じさせることです。彼を変える原動力は外圧(彼女との別離・裁判所命令・警察拘置etc)だけです。”
彼らにとっては、変わることへの努力をするより、そのままでいるほうが様々な意味で楽なのですから。
ですから、被害者は一刻も早く、別離の準備をしてください。
ただ、加害者から離れることは困難なことです。
そこで、安全に離れるには、安全性を考えた計画を立てることです。
計画には、①“相手と一緒に居ながら安全を高める計画”、②“彼のもとを離れると決めたときの計画”の二つが必要です。
安全計画を立てるにはサポートの利用を、身の安全を確保しながら法制度の利用も考えてください。(法制度の利用はかえって危険になることもあります。)
子供がいる場合は、子供にも虐待が及んでいようがいまいが即座に虐待のない環境に移す必要があります(虐待の行われている環境は、子供に多大な悪影響を及ぼします)。
ところで、そんな彼らはどのようにして作られたのでしょう。
DV加害者に生まれたのではありません。DV加害者に作られたのです。
1990年代まで、“妻への虐待を禁じる法律が執行されていなかった”という法制度の手落ちや“宗教の教えが女性への虐待を許してきた”という歴史、さらに、メディアによる男性暴力の容認などがジェンダー・バイアスとして男の子に刷り込まれています。
こんな彼らも、恋の始まりは一般人と変わりません。
虐待しようなんて考えていません。
ただ、潜在意識(コントロールしたい・特権意識を満足したい)があるだけです。
彼の目的は虐待ではなく、コントロールです。支配するために虐待する権利があると思っているのです。
そんな彼が、女性が不満を口にし始めたときから、報復を考え始めます。まず、言葉の暴力から、しだいに身体的・性的暴力へ移行します。
では、虐待に苦しむDV被害者に対して、どのように支援すれば良いのでしょうか。
支援者はまず、DV加害者と正反対の人となることです。
被害者に対して我慢強くなる必要があります(あなたの計画に従って被害者が行動することは役に立ちません。被害者の判断を尊重しなくてはなりません)。
被害者に向かって対等な人として話すことです。そして、よく聞き、あまり話さない。
また、「被害者が加害者から離れたかどうか」で支援の成否の判断をすることはやめましょう。失敗するとその不満を被害者のせいにしてしまいがちです。
支援がうまくいったかどうか把握するもっとも良い方法は、「被害者自身の人生を生きる権利」を支援者がどれくらい尊重できたかということや、「被害者がより安全になるための方法を考える」のをどれくらい助けられたかで測ることです。
そして、支援者も「最善のことをしたくて焦っている」ときは支援を得てください。支援者にとって大切な人に話してください。
我々はそろそろ、女性が侮辱されたり、侵略されたり、奪われたり、脅されたりしないで暮らす権利が守られるように、社会の価値観を変えていく必要があります。 文責 N・H
日本ホーリネス教団からの公式謝罪
辻 龍雄
グーグルで“宮本晴美”を検索すると、日本ホーリネス教団が宮本晴美さんへ宛てた謝罪文がでてきます。宮本晴美さんのお嬢さんの宮本秀美さんは、教団所属の牧師による性暴力被害者でした。牧師を相手に民事訴訟を起こし、裁判は宮本秀美さん勝訴で確定しました。しかし、勝訴判決後も牧師からは謝罪の一言もなく、賠償金の支払いにも応じませんでした。宮本秀美さんは、判決確定日から1年後に26歳で自殺されました。平成15年1月30日の読売新聞の余響の記事を読むと、自殺の知らせに対して、牧師は「私も悪いが、判決は偏っている」、その妻は「自殺は本人がしたこと。関係ない」と言い放ったと言います。事件が発覚して11年後に、ようやく、教団は公式謝罪文を平成23年の3月頃に出すと回答してきました。事件を風化させないという宮本晴美さんの決意と、“宮本の発信”という活動がもたらした公式謝罪文だと思います。
宮本秀美さんと私は、約3年間、毎日のようにメールで交信していました。秀美さんは、事件により重度のPTSDとなり、希死念慮がありました。しかし、暗い性格の女性ではなく、素顔の秀美さんは、思慮があり、しかも茶目っ気のある女性でした。真面目な女性ほど、あの手の男の餌食になるのでしょう。
秀美さんがいなくなって7年が過ぎていますが、私は、今でもありありと秀美さんの声や表情を思い出すことができます。そして、あの頃、どうしていれば、秀美さんは自殺しなかったのか? いつも私の念頭から離れないことです。
近年、自殺者の多さが社会問題化していますが、自殺を食い止めることは容易なことではありません。何度も自殺未遂を繰り返していた人の自殺さえ止めることはできなかったのです。
働くこと、職業をもつことができていれば、死ぬことはなかったのでは?と思うことがあります。また、秀美さんの周囲にいた人たち、私を含めて、裁判に勝つということを目標にしていました。しかし、これは大きな間違いでした。では、どうしていればよかったのか?
議論するという気風のようなものが、暴力や自殺の領域には、まだないのかもしれません。私たちを含めて、著名な人に来て頂いて経験談を聞くレベルなのです。議論を交わすだけの基礎資料もまだないのです。
私たちの活動は、もうじき10年になります。自分たちの経験を整理し、公表し、議論の場を作る段階に入ることができれば、対応の方法についても道が開けるのではと、私は思っています。